SONYのフルサイズミラーレス機α7シリーズのカメラを使い始めて、3年ほどが経ちました。
元々はCanonの一眼レフカメラを使っていたのですが、α7シリーズのコンパクトさに惹かれてマウント替えをしまして、現在に至ります。
決してプロではありませんが、ビジュアルにこだわった商品レビュー記事で収入を得ていたり、SNS経由で撮影のお仕事を頂くこともあり、撮影機材には結構こだわっています。
そんな僕の撮影機材に対するこだわりポイントは下記の3つ。
- 持ち歩く機材はなるべくコンパクトにする
- さまざまな撮影シーンに柔軟に対応できるようにする
- 効率よく撮影できるようにする
何度も機材のアップデートを繰り返えす中で、ようやく満足できる状態に近づいてきたので、ブロガー、フォトグラファーとして活動する僕の愛用する機材をまとめて紹介したいと思います。
撮影機材選びの参考になれば幸いです!
 一眼カメラと一緒に買い揃えたい周辺機器・アクセサリーまとめ【初心者向け】
一眼カメラと一緒に買い揃えたい周辺機器・アクセサリーまとめ【初心者向け】
タップできる目次
メイン機 Sony α7Ⅲ
現在僕がメイン機として愛用しているα7Ⅲ。写真から動画まで幅広く活躍してくれる、頼れる相棒です。
画質も満足できるし、カスタムボタンも豊富。そして、先代のα7Ⅱで不満に思っていたバッテリー持ちの悪さも解消されて使いやすいです。
発売は2018年となっていて少し型が古くなってきてはいますが、この先もまだまだメイン機として使っていく予定。
 SONY α7IIIレビュー!α7IIとの比較して進化した点を紹介
SONY α7IIIレビュー!α7IIとの比較して進化した点を紹介
サブ機 Sony α7C
メイン機のα7IIIと同等の画質を誇りながら、ボディをぐっとコンパクトに収めたのが魅力のα7C。
筐体上部がシルバーでクラシカルな雰囲気なのがカッコよくてお気に入り。
バリアングル液晶を搭載しており、操作周りが動画撮影に最適化されています。
操作周りはα7IIIの方が優秀なのでメイン機としては使っていませんが、下記のようなシーンでとても重宝しています。
- サブ機としてタイムラプスを撮影するとき
- 動画撮影をしたい時
 SONY α7C レビュー!α7IIIと比較してどっちがおすすめかも紹介
SONY α7C レビュー!α7IIIと比較してどっちがおすすめかも紹介
タムロン 大三元ズームレンズ
撮影機材のコンパクトさを追求する上で欠かせないのが、タムロンの大三元レンズ。
下記のような特徴があり、冒頭に紹介した撮影機材のこだわりポイントをすべて満たしてくれる素晴らしいレンズたちです。
- 全部揃えても30万ほどとコスパが高い(純正の場合は総額72万円ほど)
- 全部持ち出しても総重量1,780gと超軽量(純正の場合は3,046g)
- レンズ口径が67mmで揃っているのでフィルターを使いまわせる
- 操作感が統一されているからレンズ交換後も使いやすい
- 画質も良好
TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)
圧倒的なコスパの高さで発売直後から売り切れ続出となった大人気の標準ズームレンズ。
下記のような特徴を持っていて、とにかく撮影に対応できるシーンが幅広いのが特徴。初めて買うレンズはこれを買っておけば間違いないでしょう。
僕も旅行に出かける際の標準レンズにはこれを愛用しています。
- 550gの軽量なボディ
- 最短撮影19cmなので物撮りにも使いやすい
- 価格8.5万前後の安い価格設定
TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III RXDの作例
 TAMRON 28-75 F2.8 Di III RXD レビュー!ソニーEマウントのおすすめ標準ズームレンズ
TAMRON 28-75 F2.8 Di III RXD レビュー!ソニーEマウントのおすすめ標準ズームレンズ
TAMRON 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)
タムロンの大三元レンズとして2019年に発売された広角ズームレンズのTAMRON 17-28mm F/2.8 Di III RXD。
風景写真が好きなこともあり、かなりの頻度で利用しているレンズです。広大な景色やリフレクションを切り取るのに大活躍です。
下記のような点が特徴となっていて、α7シリーズのAPS-Cモードを組み合わせることでV-logの用としても大活躍する一本に仕上がっています。
- インナーズームレンズ採用だからジンバルに取り付けるのにも最適
- 最短撮影19cmでかなり寄れる
- 420gの軽量なボディ
TAMRON 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)の作例
 TAMRON 17-28mm f2.8 レビュー!ソニーEマウントのおすすめ超広角レンズ
TAMRON 17-28mm f2.8 レビュー!ソニーEマウントのおすすめ超広角レンズ
TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)
タムロンの大三元レンズの望遠ズームレンズとして2020年に満を持して発売されたTAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VXD 。
望遠ズームレンズというと重くて旅行に持っていく気持ちになれなかったんですが、F2.8通し望遠ズームでクラス最軽量の810gを実現していることもあり、割と気軽に持ち出せるようになりました。
オートフォーカス性能の速さととろけるようなボケ味がお気に入りです。
- タムロン史上最高レベルの高速・高精度オートフォーカス性能
- 最短撮影距離0.85mの高い近接性能
- 810gの軽量なボディ
TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056) の作例
フォクトレンダー ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical III
焦点距離12mmの圧倒的な広角写真を撮ることができるフォクトレンダーの単焦点レンズ、ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical III。
決して万能なレンズではないですが、ワンポイントで活躍してくれるため、おまけ程度にリュックに忍ばせています。
- フォーカスはMFのみ
- F値はF5.6〜F22となっており暗い
- 350gの軽量なボディ
ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical IIIの作例
 フォクトレンダー「ULTRA WIDE HELIAR 12mm」レビュー!α7シリーズにおすすめの超広角単焦点レンズ
フォクトレンダー「ULTRA WIDE HELIAR 12mm」レビュー!α7シリーズにおすすめの超広角単焦点レンズ
SONY Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA
主に物撮りする際に使用しているZeissの単焦点レンズ。中心に円を描くように滲む独特なボケ味とこぶりな筐体がとても気に入っています。
惜しいなーと思う点は最短撮影距離が0.5mとなっており、接写には向かないという点ぐらいです。
- 抜群の描写力
- 早いAF性能
- 軽量コンパクトな筐体
- 最短撮影距離0.5mなのであっまり寄れない
SONY Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZAの作例
カメラバッグ Incase DSLR Pro Pack Nylon
カメラには様々な沼があると言われていますが、僕はカメラバックの沼にとても深くハマりました。過去3年ほどで購入したのはなんと7つ。笑
そんな僕が現在愛用しているのは、Incase DSLR Pro Pack Nylonという一気室のカメラバッグです。
背面のファスナーを開けば持っている機材を全て収納することができ、旅行の時は少し荷物を減らして空いたスペースに衣類を突っ込めるので一気室のバッグはかなり便利。
各収納ポケットのアクセスのしやすさも計算されており、見た目もおしゃれでいい感じ。
 Incase(インケース) DSLR Pro Pack Nylon レビュー!使いやすくてかっこいい一気室カメラバッグ
Incase(インケース) DSLR Pro Pack Nylon レビュー!使いやすくてかっこいい一気室カメラバッグ
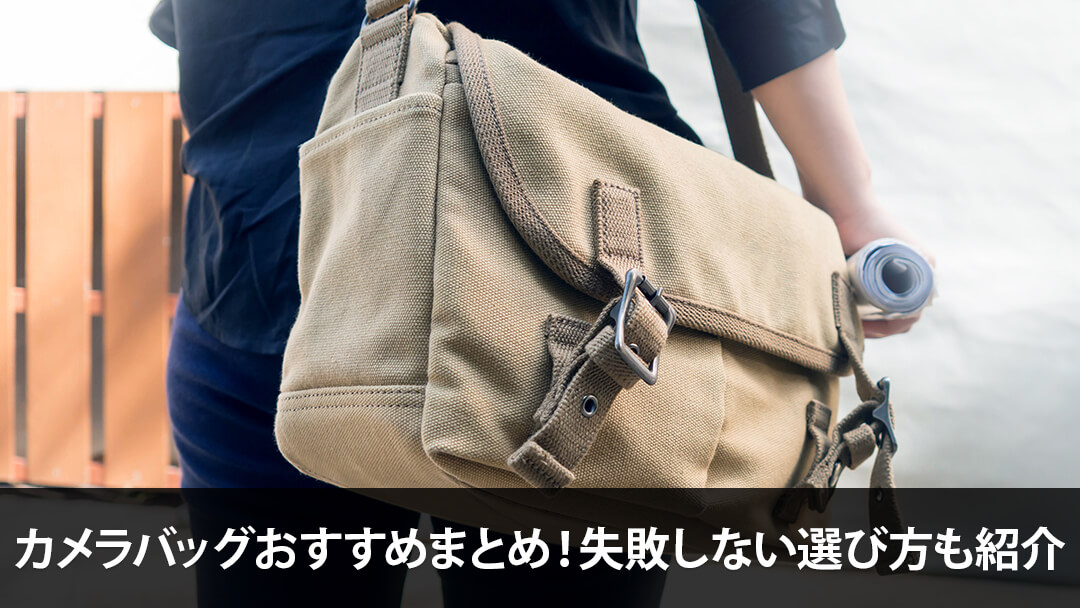 カメラバッグおすすめ14選まとめ!失敗しない選び方も紹介
カメラバッグおすすめ14選まとめ!失敗しない選び方も紹介
トラベル三脚 befreeアドバンスカーボンT三脚キット
三脚は持ち歩く撮影機材の中でももっとも重く場所をとるので、なるべく身軽に動くためにトラベル三脚を愛用し続けています。
いくつかのトラベル三脚を乗り換えた中で現在使用しているのはマンフロットのbefreeアドバンスカーボンT三脚キットです。
カーボンでできていてそれなりに軽いんですが全身高155cm、対荷重10kgとかなりしっかりしているのが特徴。
どんどん機材が小型化してきているので、そのうちもう一回りコンパクトなものに乗り換えるかもしれないですが、もうしばらくはこの三脚を愛用していきます。
 マンフロットのトラベル三脚「befreeアドバンスカーボンT三脚キット」レビュー!
マンフロットのトラベル三脚「befreeアドバンスカーボンT三脚キット」レビュー!
 【2024年】トラベル三脚のおすすめアイテムまとめ&スペック比較
【2024年】トラベル三脚のおすすめアイテムまとめ&スペック比較
卓上三脚 Leofoto MT-03+LH-25
展望台などから夜景を撮る場合や水溜りに映るリフレクションを撮る時は卓上三脚があると便利。
そこで上記で紹介したトラベル三脚とは別にレオフォトという中国のメーカーから出ているミニ三脚も持ち歩いています。
この三脚の素晴らしいところは、足を折りたたむことができて設置面の高さが均等じゃない場所でも安定して立たすことができるところ。
この柔軟に脚の角度を調整できることに今まで何度も助けられてきました。信頼が厚いミニ三脚なので今後も末永く愛用するつもりです。
 変化自在の最強ミニ三脚!Leofoto MT-03+LH-25レビュー
変化自在の最強ミニ三脚!Leofoto MT-03+LH-25レビュー
 おすすめのミニ三脚(卓上三脚)まとめ!選び方のポイントも紹介
おすすめのミニ三脚(卓上三脚)まとめ!選び方のポイントも紹介
ワイヤレスリモートコマンダー RMT-P1BT
三脚を使って撮影する場合に必須のアイテムといえばレリーズ。
サードバーティー製の有線レリーズであれば、2,000円で購入することができるのですが、僕はSONY純正のワイヤレスリモートコマンダーを使用しています。
このレリーズがあるおかげでフットワークが軽くなり、撮影が快適になりました。具体的に言うとこんな感じ▼
- レンズ交換する際にケーブルが邪魔にならない
- 撮影を開始する際にケーブルを接続する一手間が省ける
- 三脚にカメラを載せたまま移動するのが楽
- 集合写真を撮る時などに遠隔操作ができる
一度無線のレリーズの便利さを体験すると、有線には戻れないです。これは壊れたり、無くしたりしても何度でも買い直したい、それぐらいお気に入り。
 ケーブルなしでシャッターが切れる神アイテム!SONY RMT-P1BT レビュー
ケーブルなしでシャッターが切れる神アイテム!SONY RMT-P1BT レビュー
忍者レフ
展望台から夜景を撮る場合、何も対策をとらないとほとんどの場合で映り込みが発生してしまいます。
ガラス越しの夜景を綺麗にとるために使っているのが忍者レフ。
このアイテムがあれば16mm程度の広角レンズでもレンズの写り込みを防げて、クリアな夜景を撮ることができます。
唯一の欠点は展望台で忍者レフを使うとても目立つということ。一般のお客さんに邪魔にならないよう、隅っこの方で使うようにしています。
 展望台での映り込み防止に最適な撮影機材!忍者レフレビュー
展望台での映り込み防止に最適な撮影機材!忍者レフレビュー
ピークデザイン クラッチ
スナップ写真を撮る時などは基本カメラを持ったまま移動するのが好きです。ただ、何もつけずにカメラを持っていると落としてしまわないか心配になることがありました
そこで愛用しているのがピークデザインのクラッチというハンドストラップ。
取り付けやが簡単でホールド感も抜群。文句なしの使いやすさなので長く使っていくと思います。
 ピークデザイン クラッチ レビュー!スナップ撮影が快適になるおすすめハンドストラップ
ピークデザイン クラッチ レビュー!スナップ撮影が快適になるおすすめハンドストラップ
ピークデザイン キャプチャ
上記で紹介したクラッチを使用してスナップ撮影をしていると、両手を空けた状態にしたい時にカメラの置き場所に困ることがありました。
そこで購入したのが上記でも紹介したピークデザインのキャプチャ。
このアイテムを使用すると、リュックのハーネスにカメラを固定できるようになり、すぐに両手を空けた状態に切り替えることができて便利です。
 撮影が捗るおすすめカメラホルダー!Peak Design キャプチャー V3レビュー
撮影が捗るおすすめカメラホルダー!Peak Design キャプチャー V3レビュー
ヘーネル ProCube2(デュアルバッテリーチャージャー)
メイン機のα7Ⅲやサブ機のα7Cなど複数の機材を持っているとバッテリーの充電も効率よく行う必要が出てきます。
そこで購入したのがNP-FZ100バッテリーを2つまとめて充電できるProCube2というバッテリーチャージャーです。
USB-Cケーブルで充電可能ですし、充電のステータスも見やすいので、使い勝手がかなり良くてとてもおすすめです。
 ヘーネル Procube2レビュー!Sonyのミラーレス機ユーザにおすすめの最強バッテリーチャージャー
ヘーネル Procube2レビュー!Sonyのミラーレス機ユーザにおすすめの最強バッテリーチャージャー
VL81(小型照明)
部屋での撮影時に光の量が十分に足らない場合に使用している小型照明のVL81という製品。
下記のような特徴があり、とても使い勝手がいいです。
- コンパクトなサイズ感
- 明るさを自由に調整できる
- 色温度を自由に調整できる(3200k-5600k)
- バッテリー容量 3000mAh
- USB-C充電可能
HOKUTO防湿庫・ドライボックス HSシリーズ51L防湿庫
撮影機材は湿気に弱いので、カビを発生させないように保管方法には注意を払う必要があります。
機材が少なかった頃はドライボックスに機材を保管していたのですが、この運用は面倒なことが多くありました。
- 除湿剤を定期的に入れ替えるのが面倒
- 機材の出し入れしづらい
そこで購入したのがHOKUTOの防湿庫。カメラ3台、レンズ6本くらいが入る中型サイズのアイテムです。
防湿庫って高いイメージがありましたが、このアイテムは値段は1万5千円くらいで手が出しやすいです。
記事執筆時点で使用して半年ほどが立ちますが、とくに不満点もなく買ってよかったなーと思っています。
SONY α7Ⅲ愛用のブロガー&フォトグラファーの撮影機材・アクセサリーまとめ
夜景フォトグラファーの僕が愛用している撮影機材をまとめて紹介してきました。
どれもこだわり抜いて選んだアイテムたちなので、とても愛着がありますし、使い勝手も素晴らしいです。
気になったアイテムがあればぜひ購入して、撮影環境のアップデートを図ってみてもらえればと思います。



























































